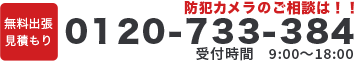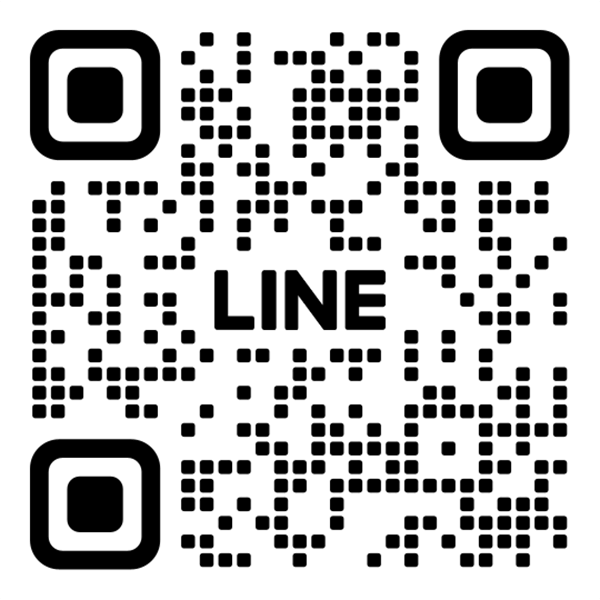学校の危機管理とは?
不審者・災害・SNSに備える実践対策と防犯設備
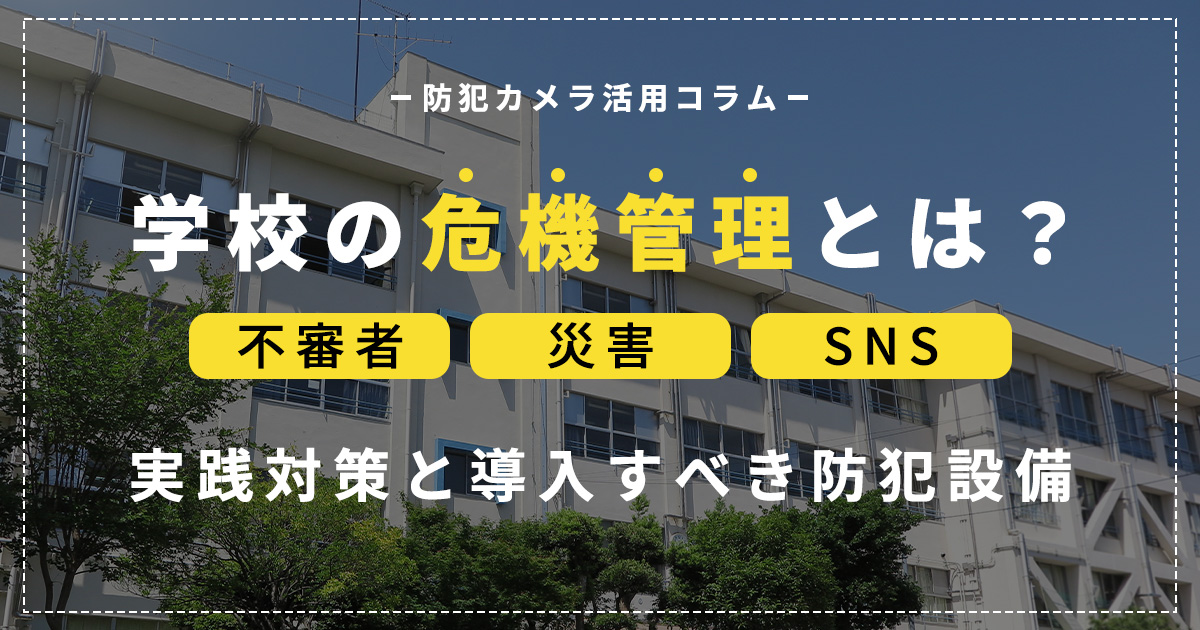
学校では、不審者の侵入や自然災害、SNSでの炎上など、いつ起きてもおかしくない危機があります。
万一の時に備えて、学校には適切な体制づくりと、すぐに動ける仕組みが欠かせません。
この記事では、学校に求められる危機管理の基本から、リスクマネジメントやクライシスマネジメントの考え方をわかりやすく解説します。
さらに、防犯カメラや入退室管理システム、110番通報装置、防犯フィルムなど、安心を守るために役立つ設備も紹介します。
この記事でわかること
- 生徒を守るために学校が取り組むべき危機管理の考え方
- 具体的な防犯設備の導入メリット
- 生徒を守り、信頼される学校になるための方法
学校の危機管理とは?基本を押さえる
学校の危機管理とは、児童生徒や教職員の安全を守るために、起こり得るあらゆるリスクに備える取り組みのことです。
では、実際に学校ではどのような危機が想定されるのでしょうか。
ここでは、学校における危機管理の主な範囲と、その対応に必要な基本の考え方を整理してみます。
学校における危機管理の主な範囲

学校では、次のようにさまざまな危機が起こり得ます。
- 自然災害(地震・台風・豪雨など)
- 感染症(インフルエンザ・食中毒など)
- 事故や不審者対応(校内での怪我・外部からの侵入)
- SNSの取り扱い(炎上・情報漏えい・緊急時の情報発信)
これらの危機は、いつ・どこで発生するか予測が難しいものです。
そのため、日ごろからの備えと体制づくりが重要です。
危機管理の2つの考え方(リスクマネジメントとクライシスマネジメント)

学校の危機管理には、大きく分けて2つの考え方があります。
- リスクマネジメント:危険が起きる前に、あらかじめ予防しておく取り組み
- クライシスマネジメント:危険が発生した後に被害を最小限に抑える対応
どちらか一方だけでは、十分な危機管理にはなりません。
予防と対応の両方をしっかり整えることが、学校全体の安全を守るカギになります。
この取り組みは子どもたちの安心につながるのはもちろん、保護者や地域からの信頼を得るうえでも大切です。
学校におけるリスクマネジメントの基本
学校の危機管理において、まず大切なのは事前に危険を予防する「リスクマネジメント」です。
リスクを正しく把握し、備えを整えておくことで、事故やトラブルを未然に防ぐことができます。
学校で予防できる主なリスクとは?
- 感染症(インフルエンザ・ノロウイルス・食中毒など)
- 手洗い・消毒・換気・給食管理などの徹底で発生を減らせます。
- 校内での事故(運動中のけが・実験や作業中の事故など)
- 安全指導や設備点検、危険箇所の改善によって未然に防止可能です。
- 不審者対応(外部からの侵入)
- 防犯カメラ・入退室管理・フェンスや施錠などで侵入を防げます。
- 情報関連のリスク(SNS炎上・個人情報漏えい)
- 情報モラル教育・アカウント管理・校内ルールの整備で予防できます。
学校におけるリスクマネジメントの対応フロー
リスクマネジメントは、思いつきで行うのではなく、一定の流れに沿って進めることが大切です。
学校では、次のようなフローで取り組むと効果的です。
- 1.リスクの洗い出し
- 校内外にどのような危険があるかを把握します。
- 2.リスクの評価
- 発生する可能性と影響の大きさを見極めます。
- 3.対策の実施
- ルール作成、教職員や児童生徒への指導、訓練、設備整備などを行います。
- 4.定期的な見直し
- 訓練結果や実際の事例をふまえて改善を繰り返します。
この流れを回し続けることで、事故やトラブルを未然に防ぎやすくなります。
設備投資によるリスク低減(防犯カメラ・防犯フィルムなど)

人の意識やルールだけでは限界があります。
そのため、設備の導入によるリスク低減もあわせて検討することが大切です。
- 防犯カメラ:校内外を監視・記録し、不審者の侵入やトラブルを抑止
- 電気錠・電磁錠:校門や出入口を遠隔で管理でき、来校者を職員が確認してから解錠できる仕組み
- 防犯フィルム:窓ガラスの破壊や侵入を防ぎ、被害を最小限に抑える
これらの設備を導入することで、目に見える安心感をつくり出すことができます。
また、保護者や地域にとっても「安全な学校だ」という信頼につながります。
トータルで学校の防犯対策をご提案
弊社では、学校の環境に合わせた総合的な防犯対策をご提案しています。
防犯カメラ・防犯フィルム・電気錠や電磁錠など、学校に必要な防犯設備の導入に対応可能です。
「うちの学校にはどんな設備が必要だろう?」
そんな疑問や不安にも、専門スタッフが無料でご相談を承ります。
学校におけるクライシスマネジメントの重要性
クライシスマネジメントとは、事故や事件、災害などが実際に起きた後に、被害を最小限に抑えるための取り組みです。
いくら予防をしていても、すべての危険を完全に防ぐことはできません。
だからこそ、「起きてしまったときにどう対応するか」こそが学校にとって大切な課題になります。
具体的には、
- 初動対応(状況把握・通報・避難誘導など)
- 情報発信(保護者や地域への迅速かつ正確な連絡)
- 再発防止策(原因分析・マニュアルの見直し)
といった流れを、日ごろから準備しておく必要があります。
この体制を整えることで、生徒の安全を守るだけでなく、学校への信頼を失わずにすむのです。
状況別に見る初期対応(災害・不審者・事故など)
クライシスマネジメントの中でも、初期対応はとても重要なポイントです。
ここでは、状況別に初期対応の流れを整理しました。
自然災害発生時の初期対応
| 災害の種類 | 初期対応のポイント |
|---|---|
| 台風・大雨 |
|
| 火災 |
|
| 地震 |
|
大切なのは「迷わず動ける準備」です。
事前にフローチャートや訓練で確認しておくことで、初動の混乱を防げます。
けが人・急病人発生時の初期対応
| 流れ | 初期対応のポイント |
|---|---|
| 発見者の役割 |
|
| 複数教職員での対応 |
|
| 外部への通報・連絡 |
|
日ごろから役割分担や通報手順を確認しておくことが、混乱を防ぐ最大のポイントです。
不審者対応で事前に決めておくべきフローチャート
学校で不審者を発見した際には、あらかじめ対応の流れを決めておくことが大切です。
以下のようなフローチャートを作成・共有しておくと、緊急時にも迷わず動けます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 不審者の判別 | どのような言動や状況を「不審」とみなすのかを学校内で統一しておく |
| 対応の役割分担 | 誰が通報するのか、誰が児童を避難させるのか、誰が校長に報告するのかを明確にしておく |
| 対応上の注意点 | 一人で対応しない/相手に背を向けない/不審物には触れない などを全職員で共有 |
| 通報・連絡のルート | 110番・119番の通報手順、学校設置者・教育委員会・保護者への連絡フローを決めておく |
| 児童生徒の避難先と方法 | 校内での安全な場所や避難経路を明示しておく |
不審者侵入時に力を発揮する110番通報装置

不審者が侵入したときに、すぐに警察へ通報できる仕組みを整えておくと安心です。
110番通報装置は、緊急時にボタンを押すだけで警察につながる防犯設備です。
近年の不審者侵入事件を受けて、幼稚園・保育園・学校など子どもが集まる教育施設で導入が増えています。
この装置を備えておけば、慌てず確実に通報でき、警察の到着を早めることができます。
学校で整備すべき危機管理マニュアルとは?
学校では、事故や災害などが発生した際に教職員が円滑かつ的確に対応するためのマニュアルを整備することが求められています。
この「危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)」は、学校保健安全法に基づき、すべての学校で作成が義務付けられているものです。
文部科学省は、事件や事故、自然災害への対応に加え、近年の学校や児童生徒を取り巻く安全上の課題を踏まえて、従来の参考資料を改訂し、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」を作成しました。
この手引きには、基本的な対応の方法や留意点が大幅に追記されており、各学校がマニュアルを見直す際に役立ちます。
出典:文部科学省「学校の危機管理マニュアル作成の手引」の作成について例:東京都教育委員会の取り組み
東京都では「学校危機管理マニュアル」を公開し、以下のように危機ごとに具体的な対応をまとめています。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 自然災害編 |
|
| 不審者侵入時の安全確保 |
|
| 事故対応編 |
|
このように、危機の種類ごとに「事前・初動・事後」の流れを決めておくことが重要だとわかります。
設備とマニュアルを連動させる重要性

危機管理マニュアルは、現場の行動と設備の使い方を結びつけてこそ意味があります。
例えば、マニュアルに「不審者を発見したら110番通報」と記載しても、110番通報装置の場所や使い方が共有されていなければ、実際には機能しません。
同じように、
- 防犯カメラ:どの職員が映像を確認し、誰に報告するのか
- 電気錠・入退室管理システム:施錠・解錠の権限を誰が持つのか
- 防犯フィルム:万が一割られた場合の二次対応(避難経路や安全確保)
といった流れをマニュアルに組み込むことで、設備を「見せかけ」ではなく「使える仕組み」に変えることができます。
保護者も安心できる、学校の危機管理を支える防犯設備

学校に防犯設備を導入することは、児童生徒の安全を守るだけではありません。
「学校がしっかり対策をしている」という姿勢が保護者の安心感につながり、地域からの信頼を高めることにもつながります。
ここでは、学校の危機管理を強化するために役立つ代表的な防犯設備をご紹介します。
不審者侵入やトラブルを抑止:防犯カメラ

防犯カメラは、不審者侵入や校内トラブルを抑止・記録するために欠かせない設備です。
設置しておくことで、児童生徒の安全を守るだけでなく、保護者にとっても大きな安心材料になります。
設置場所の例としては、次のようなポイントがあります。
- 校門:来校者の確認、不審者の早期発見
- 玄関:出入りの記録、入退室管理との連動
- 廊下:児童生徒の安全確保、トラブルの抑止
- 駐輪場・駐車場:盗難・不審者対策
このように、防犯カメラは学校の危機管理を支える必須の設備であり、同時に保護者からの信頼を高める役割も担います。
災害時の二次被害も防止:防犯フィルム

窓ガラスに防犯フィルムを貼ることで、ガラスを割って侵入する犯行を防ぎやすくなります。
とくに「CPマーク」がついた防犯フィルムは、防犯性能が公的に認められた製品で、より高い安心感があります。
導入のメリット
- 侵入にかかる時間を長引かせる
- 透明で見た目に違和感がない
- 災害時にガラスの破片が飛散するのを防ぐ
防犯フィルムは、防犯だけでなく自然災害への備えとしても有効です。
とくに人の出入りが多い窓や、大きな窓を持つ場所には、早めの導入をおすすめします。
入退室管理を徹底:電気錠・電磁錠

電気錠・電磁錠は、来校者の出入りを管理し、不審者の無断侵入を防ぐための設備です。
導入のメリット
- 電気錠:遠隔操作で解錠可能。来校者を確認してから入場できるので安心。
- 電磁錠:既存の門扉に後付けでき、比較的簡単な工事で導入可能。工事費用や手間を抑えられる。
- 耐久性・防水性:屋外でも長期間安心して利用できる。
電気錠・電磁錠を導入することで、学校の入退室管理を徹底し、保護者にとっても安心できる環境を整えられます。
防犯設備を導入する際のポイント
学校に防犯設備を導入するときは、ただ設置するだけでは安心とは言えません。
設備を本当に役立てるためには、次のようなポイントを意識することが大切です。
- 設置場所に合っているか:校門・廊下・体育館など、場所に合わせて適した機能を選ぶ
- 使いやすさ:教職員がすぐに使え、緊急時にも迷わず操作できるかどうか
- 費用の見通し:初期費用だけでなく、月々の費用や点検・修理にかかる費用も考えておく
- 防犯効果の組み合わせ:カメラ・電気錠・防犯フィルム・通報装置をバランスよく組み合わせることで効果が高まる
- 保護者や地域の安心感:しっかり備えていることを示すことで、学校への信頼が大きくなる
これらを踏まえたうえで、学校に合った設備を専門家と一緒に選ぶことが安心につながります。
弊社では、学校の環境に合わせたセキュリティプランを、知識と経験のあるスタッフが丁寧にご提案しています。
「何から始めればよいか分からない」という場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
現地調査もお見積りも無料!お気軽にご相談ください
学校の防犯カメラは初期費用0円のレンタルがおすすめ

防犯対策は必要と感じていても、費用がネックになっていませんか?
トリニティーの防犯カメラレンタルなら、初期費用0円・月々定額料金で始められます。
レンタルの安心ポイント
- 初期費用0円で導入可能:カメラ・レコーダー・設置工事までコミコミ
- 保守・サポート込み:故障時の出張修理やHDD交換も無料対応
- 定額制で安心:急な出費がなく、経費計画も立てやすい
防犯カメラを設置することで、児童生徒の安全を守るだけでなく、保護者にとっても大きな安心につながります。
「どの場所に設置すればいいかわからない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
学校現場で今日から始められる危機管理の取り組み
防犯設備を整えることはとても大切です。
しかし、設備だけでは学校の危機管理は十分とは言えません。
日々の意識や体制づくりがあってこそ、設備の効果も最大限に発揮されます。
日頃からできる取り組み
- 教職員で防犯意識を共有し、定期的にマニュアルを見直す
- 避難訓練・不審者対応訓練を実施し、緊急時に動ける体制を整える
- 校内で「危険になりやすい場所」を把握し、重点的に巡回や照明整備を行う
- 保護者や地域と連携し、情報共有のルートを確認しておく
毎日の小さな積み重ねが、大きな安心と安全を生む力になります。
先生も子どもたちも「安心できる学校」で過ごせるように、今日から一歩ずつ取り組んでいきましょう。
まとめ 学校の危機管理は「設備」と「日常の備え」の両立が大切
学校の危機管理とは、児童生徒や教職員の安全を守るために、起こり得るあらゆるリスクに備える取り組みです。
自然災害、不審者侵入、SNSのトラブルなど、予測できない危機はいつでも起こり得ます。
そのためには、
- 防犯カメラ・電気錠・防犯フィルム・110番通報装置などの設備による対策
- 日常の意識や訓練、地域との連携による備え
この2つを組み合わせることが欠かせません。
学校がしっかりと危機管理に取り組むことで、子どもたちの安全を守るだけでなく、保護者や地域からの信頼にもつながります。
トリニティーでは、学校向けの防犯カメラを初期費用0円から導入できるレンタルプランをご用意しています。
まずはお気軽にご相談ください。
現地調査もお見積りも無料!お気軽にご相談ください